ワークショップの設計は、単なる「アイデア出し」にとどまらない。成果を実現に結びつけるためには、正しい「手段」と「目的」を理解し、参加者との深い対話を生み出す方法を知ることが重要です。この記事では、ワークショップ設計における革新的なアプローチを3つの具体例をもとに紹介し、より効果的な「学びの場」の作り方をお伝えします。
ワークショップ設計の新常識成果を生むために必要なこと
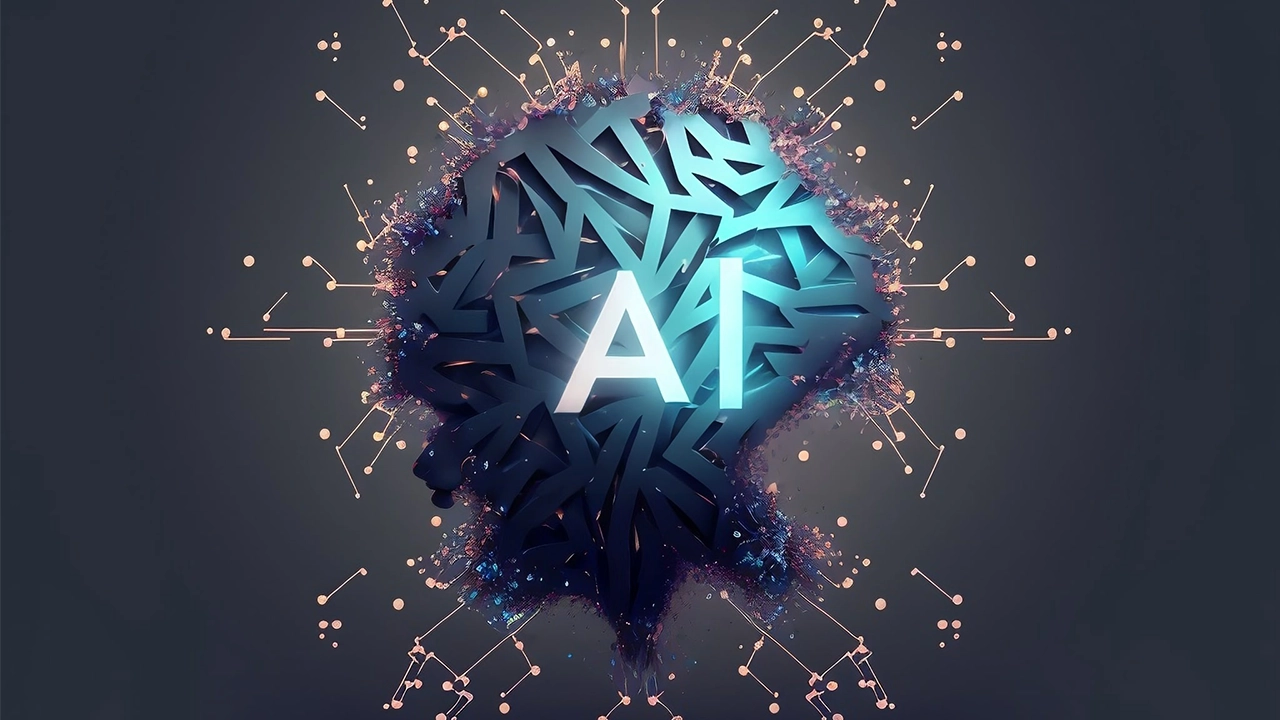
AIのイメージ
ワークショップがただの「お遊び」で終わらないためには、設計の段階でしっかりとした目標と仮説を立てることが不可欠です。では、ワークショップはどのように設計すべきでしょうか?
ワークショップの最大の目的は、参加者が集まり議論を交わすことですが、その結果として生まれる「実現可能なアイデア」こそが重要です。単に意見を聞くだけではなく、「どうすれば実現できるか」を深掘り、より効果的な方法を模索する姿勢が求められます。ここで重要なのは、“目的”を明確に持つことと、それを達成するための「ジェネレーター」の視点です。
成功するワークショップ設計手法3選
フューチャー・ランゲージ未来のビジョンを言語化する
ワークショップの参加者が持つ未来への希望やビジョンを明確に言語化することで、より具体的な行動に結びつける手法がフューチャー・ランゲージです。この手法では、現実の課題と理想の未来を対比させ、そこから「解決策」を導き出すことで、未来像を具体的な言葉として共有します。
例えば、参加者が「理想の未来」について自由にアイデアを出した後、その中から「現実の課題」を洗い出し、それに対応する解決策を導き出す過程が重要です。このフローを繰り返すことで、参加者は「未来の言葉」を創り出し、共有する力を養うことができます。
アイデア100個出し量から質へ
次に紹介するのは、「アイデア100個出し」という手法です。こちらは、テーマに関連するアイデアを数百個にわたって出し合うことで、その中から革新的で実現可能なアイデアを見つけ出す方法です。
アイデア出しの目的は「量は質に転化する」という信念に基づき、最初から絞らずに全てのアイデアを出し切ることです。アイデアの段階で質を求めず、まずはアイデアを大量に出し、その中からブラッシュアップしていきます。そのプロセスを通して、発想力が広がり、まったく新しい発想が生まれることが多いです。
レゴ®シリアスプレイ®手を動かして思考を可視化
最後に紹介する手法は、レゴ®シリアスプレイ®です。これは、レゴブロックを使って未来の街やアイデアを形にする手法で、参加者同士が視覚的に、そして体験的に未来を感じることができる方法です。
手を使って何かを作る過程で、思考は自然に深まります。この手法では、「人格と切り離して表現する」という点が特徴です。レゴ作品を使うことで、恥ずかしさや遠慮が解消され、参加者は自分の意見を自由に表現できます。これにより、個々の直感や潜在的な思いが表面化し、真の参加意識を引き出すことができます。
ChatGPTワークショップ設計に関する疑問解決
Q: どのワークショップ手法を選べばいいのか?
ワークショップの目的によって最適な手法は異なります。もし、参加者の未来像を具体的に描きたいのであれば、「フューチャー・ランゲージ」が有効です。一方で、アイデアを大量に出して選別し、具体的な行動に結びつけたい場合は「アイデア100個出し」が効果的です。参加者が積極的にアイデアを出すのが苦手な場合は、レゴ®シリアスプレイ®を使って、手を動かすことで発言を促進するのが有効です。
Q: ワークショップで結果を出すために最も大切なことは?
重要なのは、「目的を明確にし、進行中も柔軟に仮説を修正する」ことです。ワークショップでは、最初に仮説を立て、進行中に出てきたアイデアや意見を元に仮説を修正することが求められます。参加者を巻き込みながら、少しずつ形にしていくことで、より現実的で実行可能な解決策が生まれるのです。
まとめ
ワークショップは単なる「集まり」ではなく、未来を共創し、具体的な行動に結びつける場です。成功するためには、参加者との対話を通じて仮説を検証し、具体的なアイデアを創り出すプロセスが不可欠です。フューチャー・ランゲージ、アイデア100個出し、レゴ®シリアスプレイ®といった手法を活用し、参加者が一緒に「未来を動かす」経験を作り上げましょう。ワークショップを設計する際は、参加者の意見を引き出し、共創を促進する「ジェネレーター」としての立場を大切にしましょう。



コメント