API仕様書を効率的に作成する方法を探しているあなたへ。API設計書は、システム開発において非常に重要なドキュメントです。しかし、手作業での作成や更新は時間がかかり、手間も大きな負担になります。そこで注目したいのが、生成AIを活用したAPI設計書の自動生成技術です。
本記事では、Gemini CLIを使用したAPI設計書の自動生成に挑戦した実績を元に、具体的なプロンプト作成方法や、GitHub Copilotとの比較を通じて、どちらが実際の開発環境において有効かを検証します。AIを使いこなすことで、どれだけ効率化できるのか、どんな実践的な知見が得られたのか、さらにプライバシー面でのリスク管理についても詳しく解説します。
API設計書の自動生成に挑戦!Gemini CLIとGitHub Copilotの比較
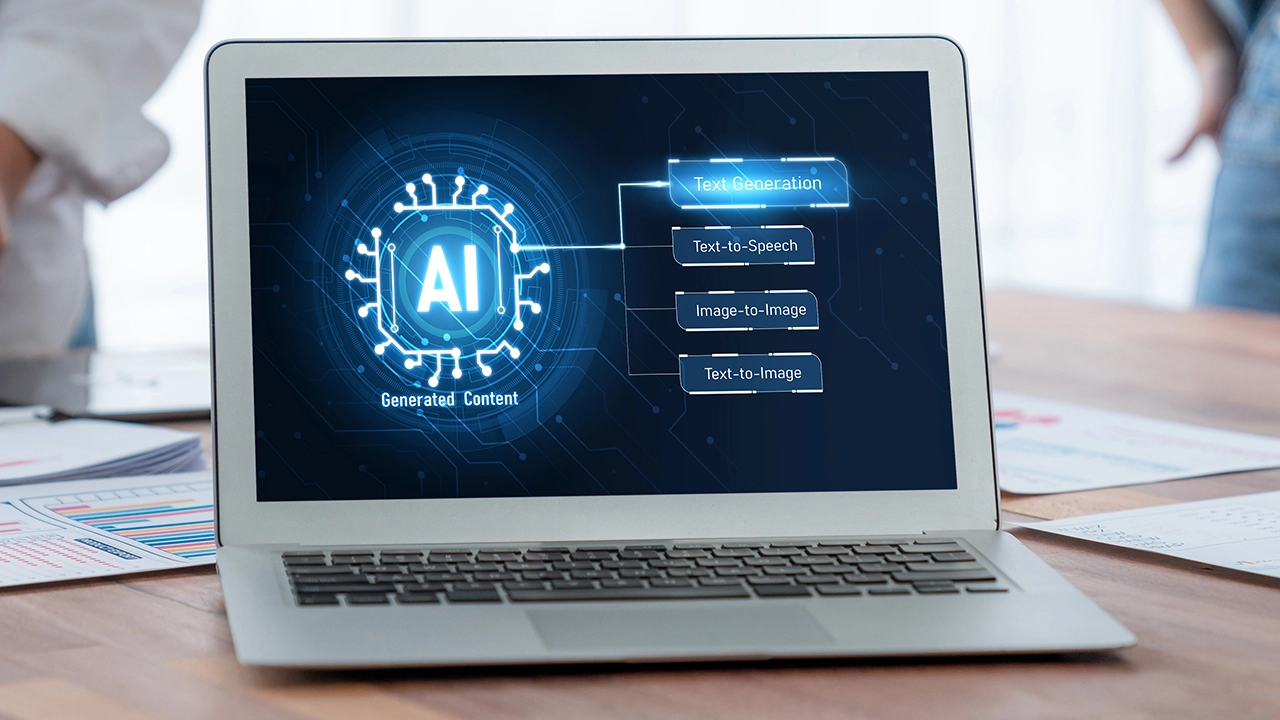
AIのイメージ
API設計書はシステム開発における重要な指針となりますが、手作業での作成や更新には膨大な時間がかかります。この問題を解決するため、私は生成AIを活用することを決めました。Gemini CLIとGitHub Copilot Chatを使い、どちらが実用的かを比較してみました。
Gemini CLIによるAPI仕様書自動生成
Gemini CLIを使って、API仕様書を自動生成するためには、まずプロンプトを作成する必要があります。長文のプロンプトを直接入力するのは非現実的なので、テキストファイルでプロンプトを指定しました。これにより、AIが適切に理解し、精度の高いAPI仕様書を生成できるのです。
実際に生成したAPI仕様書のサンプルは、かなり完成度が高く、基本的な項目が網羅されていました。しかし、依然として細かい修正が必要な場合もあるため、プロンプトを調整することで、さらに改善が可能でした。
GitHub Copilot Chatとの違い
GitHub Copilotは、VS Codeと密に連携しているため、コード補完や自動生成の際に非常に強力です。API仕様書生成においても便利ですが、Gemini CLIの方がより「ドキュメント重視」であり、情報の整理や構造化には適していると感じました。GitHub Copilotはコード生成を主体とするツールなので、用途が少し異なるため、比較には工夫が必要でした。
生成AIを使う際のセキュリティリスクと対策
生成AIを利用する際には、セキュリティリスクを避けることも重要です。プライベートなソースコードを解析する場合、AIがそのコードを学習データとして使用するリスクが考えられます。Gemini CLIの無料版では、プロンプトに「No」を選択することで、学習データに利用されない設定にできます。これにより、プライバシーリスクを避けることが可能です。
対話型でのプロンプト入力と長文プロンプトの注意点
Gemini CLIでは、長文プロンプトを入力する場合には、ファイルとして運用することを強くお勧めします。これにより、逐次的にプロンプトを投げるよりも精度が向上します。しかし、ファイルとして運用する際も、トークン数制限や起動ディレクトリの制約に注意が必要です。
Gemini API設計書の作成に役立つプロンプト例
API設計書を生成するためのプロンプトには、いくつかのコツがあります。これを理解し、実際に使えるプロンプトを作成することで、より効率的に高品質なドキュメントを得ることができます。
プロンプト作成のコツ
- 明確で具体的な指示を与える
- ドキュメント構造を事前に整理しておく
- 生成されたアウトプットを精査し、修正依頼を出すことを前提にする
これらを意識することで、生成AIを用いたAPI設計書作成がよりスムーズになります。
Gemini API設計書に関する疑問解決
Q1. Gemini CLIの無料版ではどんな制限がありますか?
Gemini CLIの無料版では、対話型プロンプト入力やトークン数制限にいくつかの制約があります。また、起動ディレクトリ配下しか参照できない点も注意が必要です。
Q2. CopilotとGemini CLIはどちらが優れているのでしょうか?
用途により異なりますが、GitHub Copilotはコード補完や自動生成に強力で、開発中のコードに直接組み込む場合に最適です。一方、Gemini CLIはドキュメント作成に特化しており、API仕様書や技術文書の生成にはこちらの方が優れています。
まとめ
生成AIを活用したAPI設計書の作成は、開発者にとって大きな効率化の手段となります。Gemini CLIとGitHub Copilot Chatの使い分けを理解し、セキュリティリスクにも配慮しながら活用することで、より良いドキュメントを作成することが可能です。プロンプト作成のコツや実践的なアドバイスを参考に、あなたも生成AIを使ったドキュメント生成に挑戦してみましょう!
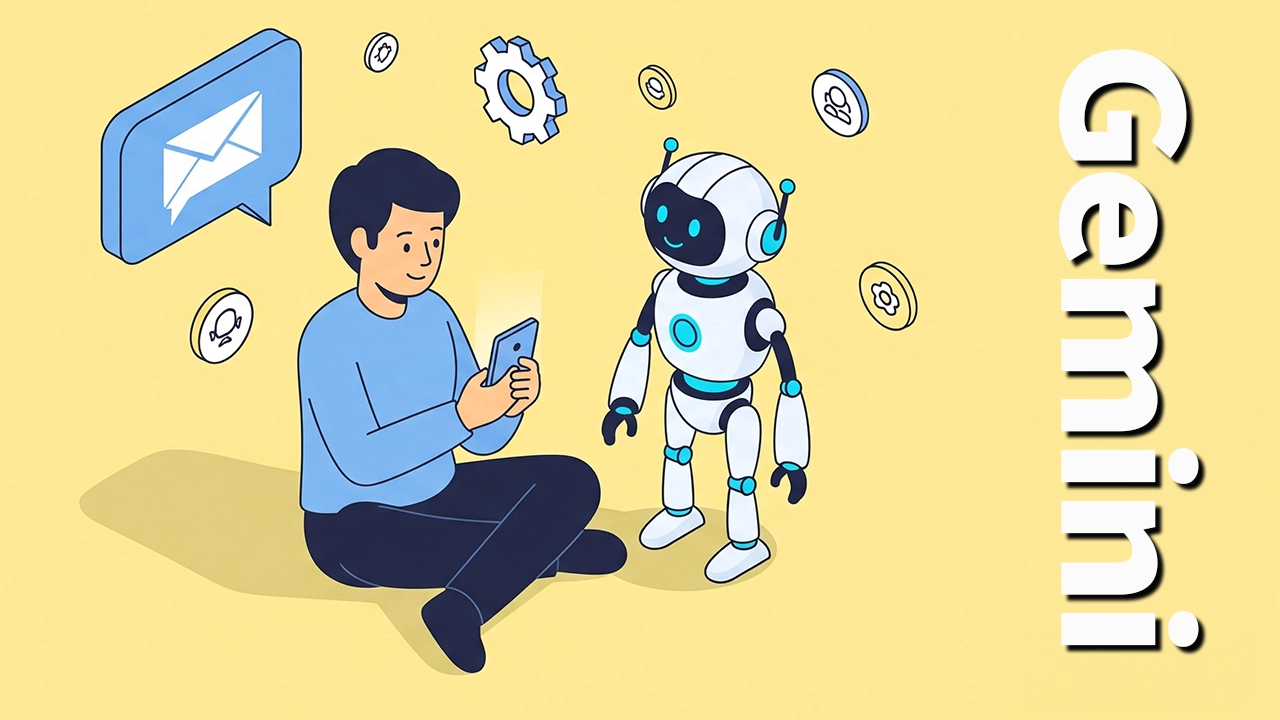


コメント