サーバーレスという言葉を聞いたことはありますか?アプリケーションを動かすのにサーバーの管理が不要で、アクセスがない時は料金も発生しない。そんな夢のような仕組みが、GoogleCloudが提供するCloudRunなのです。しかし、実際に使いこなすにはどうすればいいのか、2026年の最新アップデートで何が変わったのか、気になりますよね?
本記事では、CloudRunの基礎知識から実践的な使い方、さらには2026年2月時点の最新情報まで、初心者の方でも理解できるよう徹底的に解説します。この記事を読めば、CloudRunを使った開発の第一歩を自信を持って踏み出せるはずです。
- CloudRunはサーバー管理不要でコンテナアプリを動かせるフルマネージドPaaS
- 2026年最新アップデートでNVIDIA L4 GPUとRTX PRO 6000 Blackwell GPUをサポート
- 新しい実行モデルWorkerPoolsでプル型ワークロードにも対応可能
CloudRunとは何か?サーバーレスの革命

AIのイメージ
CloudRunは、GoogleCloudが提供するフルマネージド型のコンテナ実行環境です。コンテナ化されたアプリケーションを簡単にデプロイでき、アクセス数に応じて自動的にスケーリングする仕組みを持っています。
従来、アプリケーションを公開するには、サーバーを自分で用意し、ユーザーのアクセスに対応できるように設定・管理する必要がありました。サーバーのOS更新、セキュリティパッチ適用、負荷分散の設定など、開発者は多くの時間をインフラ管理に費やしていたのです。
しかしCloudRunを使えば、これらの作業をすべてGoogleCloudが代行してくれます。開発者はアプリケーションの開発そのものに集中でき、サーバー構築や運用保守の負担から解放されます。このような仕組みは、PaaS(Platform as a Service)と呼ばれています。
さらに注目すべきは、CloudRunが提供するサーバーレスアーキテクチャです。サーバーレスとは文字通り「サーバーを意識しなくて良い」という意味で、インフラの管理を完全にクラウドプロバイダーに任せられる開発モデルを指します。
CloudRunでは、2026年2月現在、3つの主要な実行モデルが提供されています。HTTPリクエストを処理するCloudRunServices、バッチ処理を実行するCloudRunJobs、そして新たに追加されたCloudRunWorkerPoolsです。WorkerPoolsは、KafkaやPub/Subなどのプル型ワークロードに特化した実行モデルで、HTTPエンドポイントを必要とせず、継続的なバックグラウンド処理に最適化されています。
CloudRunが選ばれる5つの理由
なぜ多くの開発者がCloudRunを選ぶのでしょうか?その理由を5つの視点から解説します。
第一に、自動スケーリング機能です。アプリケーションへのアクセスが急増すると、通常のサーバーでは処理能力の限界を超えてしまい、アクセス不可やレスポンス低下などの不具合が発生することがあります。CloudRunでは、アクセス数に応じて自動的にコンテナの数を調整する仕組みが提供されており、安定してアプリケーションを運用できます。
また、深夜などアクセスがほとんどない時間帯には、自動的にインスタンスをゼロにスケーリング(停止)し、無駄なコストを削減できます。これをゼロスケーリングと呼びます。ただし、ゼロスケーリング状態から初回のアクセス時には、インスタンスの起動時間(コールドスタート)が発生し、数秒程度の遅延があることに注意が必要です。
第二に、従量課金制です。CloudRunは、アプリケーションが動作していない間は料金が発生しません。実際にアプリケーションがリクエストを受け取り、処理を行った時間やリソース使用量に応じて課金される仕組みです。アクセスがない時間帯にはコストがかからないという、非常に効率的な課金モデルになっています。
第三に、簡単なデプロイプロセスです。デプロイとは、開発したアプリケーションを実際に動かせる環境に配置して、利用できる状態にする作業のことを指します。CloudRunでは、デプロイを開始するとわずか数十秒でURLが自動発行され、作成したアプリケーションをすぐにブラウザで確認できます。
さらに、CloudRunではソースコードだけを用意すれば、Dockerfileがなくてもデプロイすることが可能です。コードをそのまま指定するだけで、CloudRunが自動的にビルドの手順を判断し、アプリケーションを公開してくれます。コンテナの知識がなくても、すぐに始められるのが大きな魅力です。
第四に、言語とフレームワークの柔軟性です。CloudRunはコンテナベースで動作するため、どんな言語やフレームワークでも実行可能です。Node.jsやPython、Go、Javaはもちろん、RustやPHP、さらに自作のバイナリやDartなど多様な環境に対応しています。CloudFunctionsやAppEngineは対応言語が限られていますが、CloudRunは「コンテナさえ動けば基本何でもOK」という柔軟性を持っています。
第五に、充実したセキュリティ機能です。CloudRunは自動でHTTPSに対応しており、SSL証明書の設定は不要です。IAM(Identity and Access Management)との連携により、誰がアクセス・操作できるかを細かく制御できます。また、CloudRun同士やCloudFunctions、Workflowsなどのサービスとトークンベースで安全に連携することも可能です。
2026年の最新アップデートでは、SecurityCommandCenterとの連携が強化され、CloudRunで実行されているアプリケーションに対してニアリアルタイムの脅威検出が可能になりました。コンテナエスケープや悪意のあるバイナリの実行などを検出する「ランタイム検出」と、不審なIAM設定変更などを検出する「コントロールプレーン検出」の2種類が提供されています。
CloudRunの料金体系を徹底解説
CloudRunの料金体系は、CPU使用時間、メモリ使用量、リクエスト数の3つの要素で構成されています。2026年2月時点の東京リージョンにおける料金体系を見ていきましょう。
基本的な料金構造として、CloudRunはリクエストベースの課金とインスタンスベースの課金の2つのモデルを提供しています。リクエストベースの課金では、コンテナがリクエストを処理している時間のみ課金されます。標準リージョンでは、vCPU秒あたり約0.000024ドル、GiB秒あたり約0.0000025ドルという低コストです。つまり、フルvCPUで約0.086ドル/時間、1GiBのRAMで1時間1セント未満という計算になります。
また、CloudRunには毎月一定の無料枠が提供されています。2025年8月時点の東京リージョンにおける無料枠は以下の通りです。0.25vCPU・512MiBメモリ構成なら、約200時間/月まで無料で稼働できます。これは、小規模なアプリケーションや検証・学習用途であれば、無料で利用できるケースが多いことを意味します。
ネットワークエグレス(アウトバウンドデータ転送)は別途課金されますが、同じリージョン内のCloudRunサービス間のデータ送信は無料です。CloudStorageやBigQueryなど、同じリージョン内のGoogleサービスへのトラフィックも無料となっています。
2026年最新!GPU対応で広がる可能性
2026年2月時点の最も注目すべきアップデートは、GPUサポートの正式提供です。CloudRunでは、NVIDIA L4 GPU(24GB VRAM)とNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU(96GB VRAM、プレビュー版)をサポートしています。
L4 GPUは、AI推論ワークロード、特に大規模言語モデル(LLM)やその他の計算集約的な非AIユースケース(動画エンコーディング、3Dレンダリングなど)に最適化されています。従来のCPUソリューションと比較して最大120倍高いAI動画パフォーマンスを実現し、前世代と比較して2.7倍優れた生成AI推論パフォーマンスを発揮します。
GPU対応の最大の特徴は、フルマネージドで追加のドライバーやライブラリが不要という点です。GPUを搭載したCloudRunインスタンスは、約5秒で起動し、その時点でコンテナ内で実行されているプロセスがGPUを使い始めることができます。また、GPUを搭載したインスタンスも、使用されていない時はゼロにスケールダウンしてコストを節約できます。
料金面では、Tier1リージョンにおいてNVIDIA L4は、ゾーン冗長性なしで約0.0001867ドル/秒(約0.67ドル/時間)です。ゾーン冗長性ありの場合、料金は約0.0002909ドル/秒と高くなります。従量課金制のため、必要な時だけGPUを使用し、不要な時はコストをゼロにできるのが大きなメリットです。
L4 GPUを使用する場合は、最低4CPU・16GiBのメモリが必要です。RTX PRO 6000 Blackwell GPUの場合は、最低20CPU・80GiBのメモリが必要となります。対応リージョンは、us-central1(アイオワ)、europe-west1(ベルギー)、europe-west4(オランダ)、asia-southeast1(シンガポール)、asia-south1(ムンバイ)など、世界中で拡大しています。
実際のユースケースとしては、Gemma3やLlama3などの軽量LLMのホスティング、画像認識、動画エンコーディング、ストリーミングデータ処理などが挙げられます。Wayfairは「L4 GPUは優れたパフォーマンスとリーズナブルなコストプロファイルを提供します。高速な自動スケーリングと組み合わせることで、コストを最適化でき、85%のコスト削減を実現しました」と語っています。
CloudRunと他サービスとの連携術
CloudRunの真の力は、他のGoogleCloudサービスとの連携によって発揮されます。ここでは、実務で役立つ3つの連携パターンを紹介します。
SecretManagerとの連携は、機密情報を安全に管理するための必須テクニックです。APIキー、データベースのパスワード、認証トークンなどをSecretManagerで一元管理し、CloudRunから安全にアクセスできます。連携方法は主に3つあります。ボリュームマウント方式では、シークレットをコンテナ内のファイルシステムにマウントします。環境変数方式では、シークレットを環境変数として注入します。APIアクセス方式では、アプリケーションコードからSecretManager APIを直接呼び出します。
推奨されるのはボリュームマウント方式です。この方式では、デプロイ設定でシークレットの依存関係が明確になり、アプリケーションコードのポータビリティが高く保たれます。また、環境変数よりもセキュアで、プロセスダンプなどからの漏洩リスクが低減されます。
Datadogとの連携は、アプリケーションの監視と分析に不可欠です。CloudRunのマルチコンテナ機能を活用し、サイドカーとしてserverless-initを配置することで、ログ、メトリクス、トレースをDatadogに送信できます。CloudRunのマルチコンテナは同一のネットワーク名前空間を共有するため、アプリケーションがlocalhostに送信したデータは、同じインスタンス内のserverless-initが受け取り、Datadog APIに転送してくれます。
CloudLoggingとの連携も重要です。CloudRunでは、標準出力や標準エラー出力にテキストを出力するだけで、CloudLoggingにログを自動的に送信できます。さらに、JSON形式で構造化してログを出力することで、CloudLoggingでログがパースされ、閲覧しやすくなります。severity(重要度)を明示したり、複数行に渡るログを見やすく表示したり、カスタムフィールドを含ませて検索性を向上させることができます。
CloudRunの実践的な使い方
実際にCloudRunを使う際の具体的な手順を見ていきましょう。まずは基本的なデプロイ方法から説明します。
CloudRunへのデプロイは、gcloudコマンドを使用するのが最も一般的です。コンテナイメージからデプロイする場合、以下のようなコマンドを実行します。このコマンドは、指定したコンテナイメージをCloudRunにデプロイし、自動的にHTTPSエンドポイントを作成します。リージョンを指定することで、アプリケーションをデプロイする地理的な場所を選択できます。
ソースコードから直接デプロイする場合は、さらに簡単です。CloudRunが自動的にビルドの手順を判断し、コンテナイメージを作成してデプロイしてくれます。この機能をソースベースデプロイと呼び、Dockerfileがなくても、ソースコードだけでアプリケーションを公開できます。
本番環境で運用する場合は、いくつかの追加設定を検討すべきです。まず、カスタムドメインの設定です。デフォルトでは「*.run.app」というサブドメインが割り当てられますが、独自のドメインを設定することで、よりプロフェッショナルな印象を与えられます。
次に、認証と認可の設定です。2026年の最新アップデートでは、CloudRunに対してIdentity-Aware Proxy(IAP)を有効化できるようになりました。これにより、組織内のGoogleアカウントによる認証を非常に簡単に実装できます。以前はロードバランサーを前段に配置する必要がありましたが、この統合により、単純なGoogleアカウントによる認証機能が必要な場合は非常に容易に設定可能となりました。
環境変数とシークレットの管理も重要です。環境変数は、アプリケーションの設定を外部化するための標準的な方法です。CloudRunでは、デプロイ時に環境変数を設定でき、アプリケーションコードを変更せずに設定を変更できます。機密情報については、前述のSecretManagerと連携することで、安全に管理できます。
リビジョン管理とロールバックも、CloudRunの強力な機能です。CloudRunではデプロイのたびに「リビジョン」が自動で作成され、前のバージョンにいつでも戻すことができます。これにより、問題が発生した際にすぐに前のバージョンに戻せるため、本番環境での安心感が高まります。
CloudRunWorkerPoolsの使い方も押さえておきましょう。WorkerPoolsは、2025年6月のGoogleCloudNext ’25で発表された新しい実行モデルで、2026年2月現在パブリックプレビュー段階にあります。HTTPエンドポイントを必要とせず、継続的なバックグラウンド処理に特化しています。
WorkerPoolsの最大の特徴は、プル型ワークロードに最適化されている点です。KafkaやPub/Sub、RabbitMQなどのメッセージキューからメッセージをプルして処理する、GitHub Actionsのランナーをホストする、などのユースケースに適しています。また、通常のCloudRunServicesと比較して、CPU/メモリが最大40%安価になっています。
WorkerPoolsは手動スケーリングで、インスタンス数を手動で設定する必要があります。ただし、オープンソースのオートスケーラーを使用することで、メトリクスに基づいた自動スケーリングを実装できます。例えば、Cloud Run Kafka Autoscalerは、Kafkaのオフセットラグに基づいてWorkerPoolsのインスタンス数を動的に調整します。
現場で役立つCloudRunコマンド集

AIのイメージ
実際の開発現場で使う頻度が高いgcloudコマンドを厳選して紹介します。これらのコマンドを覚えておくだけで、日々の作業効率が大幅に向上します。
サービスの状態確認では、現在デプロイされているサービスの詳細情報を確認できます。gcloud run services describe SERVICE_NAME –region REGIONというコマンドで、現在のリビジョン、メモリ設定、環境変数、トラフィック分散状況などが一覧で表示されます。特にトラブルシューティング時には、このコマンドでサービスの現在の状態を把握することが第一歩となります。
ログのリアルタイム監視は、gcloud run services logs tail SERVICE_NAME –region REGIONで実現できます。このコマンドを実行すると、サービスのログがリアルタイムで流れてきます。デプロイ直後の動作確認や、エラーの原因調査に非常に便利です。特定の時間範囲のログを確認したい場合は、–since フラグを使用して「–since 1h」とすれば過去1時間のログを表示できます。
トラフィック分散の設定も重要です。新しいリビジョンをデプロイしたとき、いきなり100%のトラフィックを流すのはリスクが高いです。gcloud run services update-traffic SERVICE_NAME –to-revisions=REVISION1=90,REVISION2=10というコマンドで、段階的にトラフィックを移行できます。これにより、カナリアデプロイやブルーグリーンデプロイメントを簡単に実現できます。
環境変数の更新は頻繁に行う作業です。gcloud run services update SERVICE_NAME –update-env-vars KEY1=value1,KEY2=value2で、複数の環境変数を一度に更新できます。既存の環境変数を削除したい場合は、–remove-env-vars KEY1,KEY2というフラグを使用します。
よくあるトラブルと解決策を体験から語る
実際の開発現場で頻繁に遭遇する問題と、その解決策を体験ベースで紹介します。これらは私自身が何度も経験し、試行錯誤の末に見つけた解決方法です。
メモリ不足エラーで503が返される問題は、初心者が最も頻繁に遭遇するトラブルです。ログには「Memory limit exceeded」というメッセージが出力されますが、一見するとアプリケーションコードの問題なのか、設定の問題なのか分かりにくいです。この問題の多くは、デフォルトのメモリ設定(512MiB)が不足していることが原因です。
解決策として、まずCloudLoggingで実際のメモリ使用量を確認します。「container/memory/utilizations」というメトリクスを見ることで、ピーク時のメモリ使用量が分かります。もし90%以上使用していたら、メモリを増やす必要があります。gcloud run services update SERVICE_NAME –memory 1Giというコマンドで、メモリを1GiBに増やせます。ただし、単純にメモリを増やすだけでなく、アプリケーション側でメモリリークがないかもチェックすべきです。
コールドスタートが遅すぎる問題も、ユーザー体験を大きく損なう課題です。特にNext.jsやDjangoなどのフレームワークを使用している場合、初回リクエストに10秒以上かかることもあります。この問題に対する最も効果的な解決策は、最小インスタンス数を1に設定することです。gcloud run services update SERVICE_NAME –min-instances 1で設定できます。
ただし、これにはコストがかかります。1インスタンスが常時稼働するため、アクセスがなくても料金が発生します。コストを抑えつつコールドスタートを改善したい場合は、コンテナイメージの最適化が有効です。マルチステージビルドを使用して不要なファイルを除外する、依存関係を最小限にする、軽量なベースイメージを使用する、といった工夫で、コンテナの起動時間を大幅に短縮できます。
環境変数がうまく反映されない問題も頻繁に見られます。環境変数を更新したのに、アプリケーションが古い値を使い続けているケースです。これは、CloudRunのリビジョン管理の仕組みが原因です。環境変数を更新しても、既存のインスタンスには反映されません。新しいリビジョンが作成され、トラフィックが新しいリビジョンに流れるまで、古い値が使われ続けます。
解決策は、環境変数を更新した後に、明示的に新しいリビジョンにトラフィックを100%割り当てることです。また、SecretManagerを使用している場合は、シークレットの新しいバージョンを作成し、サービスを更新する必要があります。単にSecretManager側でシークレットを更新しただけでは、CloudRunには反映されないので注意が必要です。
データベース接続の枯渇問題は、スケールアウト時に発生しやすいトラブルです。CloudRunは急激にスケールアウトするため、データベースの接続数上限に達してしまうことがあります。特にCloudSQLを使用している場合、デフォルトの接続数制限は意外と低く設定されています。
この問題に対しては、CloudSQLプロキシを使用することが推奨されます。CloudSQLプロキシは、コネクションプーリングを自動的に行い、効率的にデータベース接続を管理します。また、アプリケーション側でもコネクションプールの設定を適切に行うことが重要です。最大接続数は、想定される最大インスタンス数を考慮して設定する必要があります。
パフォーマンス最適化の実践テクニック
CloudRunのパフォーマンスを最大限に引き出すための具体的なテクニックを紹介します。これらは実際のプロダクション環境で効果が確認されている方法です。
同時実行数(Concurrency)の最適化は、コスト削減とパフォーマンス向上の両方に効果があります。デフォルトでは、1つのインスタンスで80のリクエストを同時処理できますが、アプリケーションの特性によって最適な値は異なります。CPU集約的な処理が多い場合は、同時実行数を低めに設定(10〜20)することで、各リクエストのレスポンスタイムが改善されます。逆に、I/O待ちが多い処理(外部APIの呼び出しなど)では、同時実行数を高めに設定(100以上)することで、インスタンス数を減らしてコストを削減できます。
CPU割り当て戦略も重要です。CloudRunでは、「リクエスト処理中のみCPUを割り当てる」モードと「常時CPUを割り当てる」モードの2つから選択できます。デフォルトはリクエスト処理中のみですが、バックグラウンドタスクやWebSocketを使用する場合は、常時CPU割り当てモードにする必要があります。gcloud run services update SERVICE_NAME –cpu-always-allocatedというフラグで設定できます。
リージョン選択の最適化も見落とされがちですが、重要な要素です。ユーザーに最も近いリージョンを選択することで、ネットワークレイテンシを最小化できます。日本のユーザーが主な場合はasia-northeast1(東京)、アジア全体をターゲットにする場合はasia-southeast1(シンガポール)が適しています。また、他のGoogleCloudサービス(CloudSQL、CloudStorageなど)と同じリージョンに配置することで、データ転送コストを削減し、レイテンシも改善できます。
静的ファイルの配信最適化では、CloudRunで直接静的ファイルを配信するのではなく、CloudCDNやCloudStorageを活用することをお勧めします。CloudRunは動的コンテンツの生成に特化しており、静的ファイルの配信には最適化されていません。画像、CSS、JavaScriptファイルなどはCloudStorageに配置し、CloudCDNでキャッシュすることで、CloudRunの負荷を軽減し、ユーザーへの配信速度も向上します。
コスト最適化の裏ワザ
CloudRunのコストを削減するための、あまり知られていない実践的なテクニックを紹介します。
リビジョンの自動削除設定は、意外とコスト削減に効果があります。CloudRunは、デプロイするたびに新しいリビジョンを作成しますが、古いリビジョンもストレージに残り続けます。これらは直接的な課金対象ではありませんが、プロジェクト全体のリソース使用量に影響します。古いリビジョンを定期的に削除することで、管理コストを削減できます。
スケジュール実行の最適化では、CloudSchedulerを使用してCloudRunを定期実行する場合、実行頻度を最適化することが重要です。例えば、1時間ごとに実行するバッチ処理を、夜間(アクセスの少ない時間帯)にまとめて実行するように変更するだけで、他のサービスへの負荷を分散し、全体的なコストを削減できます。
リージョンごとの料金差を活用することも検討すべきです。CloudRunの料金は、リージョンによって若干異なります。Tier1リージョン(us-central1など)は最も安価で、Tier2、Tier3と高くなります。サービスのレイテンシ要件が厳しくない場合は、より安価なリージョンを選択することでコストを削減できます。
CPU/メモリ比率の最適化も重要です。CloudRunでは、CPUとメモリを個別に設定できますが、適切な比率を選ぶことでコストを最適化できます。メモリ集約的なアプリケーション(画像処理など)では、CPU:メモリを1:4(例1vCPU、4GiB)に設定し、CPU集約的なアプリケーション(計算処理など)では1:2(例2vCPU、4GiB)に設定することで、無駄なリソースへの支払いを避けられます。
CI/CDパイプラインのベストプラクティス
CloudRunへの継続的デプロイメントを実現するためのベストプラクティスを紹介します。
CloudBuildとの統合が最も一般的で推奨される方法です。GitHubやGitLabのリポジトリにコードをプッシュすると、自動的にCloudBuildがトリガーされ、ビルド、テスト、デプロイが実行されます。cloudbuild.yamlファイルで、ビルドステップを定義できます。ビルド時間を短縮するために、キャッシュを活用することが重要です。Dockerイメージのレイヤーキャッシュを有効にすることで、変更のない部分は再ビルドせずに済みます。
段階的なロールアウト戦略では、新しいバージョンをいきなり本番環境に全展開するのではなく、段階的にトラフィックを移行します。まず新しいリビジョンに10%のトラフィックを流し、エラー率やレスポンスタイムを監視します。問題がなければ50%、90%、最終的に100%とトラフィックを増やしていきます。この戦略により、問題を早期に発見し、影響を最小限に抑えられます。
自動ロールバック機能の実装も重要です。新しいバージョンのエラー率が一定の閾値を超えた場合、自動的に前のバージョンにロールバックする仕組みを構築できます。CloudMonitoringのアラートと、CloudFunctionsまたはCloudWorkflowsを組み合わせることで、この仕組みを実現できます。エラー率が5%を超えたら、自動的にトラフィックを前のリビジョンに戻すといった設定が可能です。
環境ごとの設定管理では、開発、ステージング、本番環境で異なる設定を使い分ける必要があります。環境変数をGitで管理するのはセキュリティリスクがあるため、SecretManagerやConfigMapを活用します。また、Terraformなどのインフラストラクチャ・アズ・コード(IaC)ツールを使用することで、環境の再現性を高め、設定のバージョン管理も可能になります。
監視とアラートの実践的な設定
CloudRunの安定運用には、適切な監視とアラート設定が不可欠です。実際のプロダクション環境で役立つ設定を紹介します。
カスタムメトリクスの活用では、CloudRunのデフォルトメトリクスだけでなく、アプリケーション固有のメトリクスも監視することが重要です。OpenTelemetryやCloudMonitoring APIを使用して、ビジネスロジックに関連するメトリクス(ユーザー登録数、注文処理時間など)を送信できます。これらのメトリクスをダッシュボードに表示することで、技術的な問題だけでなく、ビジネス上の問題も早期に発見できます。
エラー率ベースのアラートは、最も重要なアラートの1つです。エラー率が通常の2倍になったら通知を送る、といった設定が有効です。ただし、絶対値ではなく相対的な変化を監視することで、誤検知を減らせます。例えば、「過去5分間のエラー率が、過去1時間の平均エラー率の2倍を超えた場合」といった条件設定が推奨されます。
レイテンシベースのアラートも重要です。P95レイテンシ(95パーセンタイル)が一定の閾値を超えた場合に通知を送ることで、ユーザー体験の劣化を早期に検知できます。P50(中央値)だけでなく、P95、P99も監視することで、一部のユーザーが遅延を経験している状況を把握できます。
コスト異常検知では、CloudBillingのアラート機能を活用します。月次予算の80%に達したら警告、100%を超えたら緊急アラートを送る、といった設定が基本です。さらに、日次でコストの変化を監視し、通常の2倍以上のコストが発生した場合に通知を送ることで、予期せぬスケールアウトや設定ミスを早期に発見できます。
ぶっちゃけこうした方がいい!
ここまでCloudRunの様々な機能や設定方法を説明してきましたが、正直に言うと、最初から完璧を目指さなくていいんです。私自身、最初はデフォルト設定のままデプロイして、問題が出てから調整するというアプローチを取っていました。
ぶっちゃけ、CloudRunの最大の魅力は「とりあえず動かしてみる」のハードルが異常に低いことです。Dockerfileさえあれば、5分でデプロイできます。いや、Dockerfileすらなくても、ソースコードだけでデプロイできちゃう。この手軽さを活かさない手はありません。
個人的には、最小インスタンス数1の設定は早めにやっておいた方がいいと思います。コールドスタートの問題は、実際にユーザーがアクセスするまで気づかないことが多いんです。開発中は何度もアクセスするからインスタンスが起動しっぱなしで、問題に気づかない。でも、本番リリースして数時間後にユーザーから「めっちゃ遅い」ってクレームが来る。これ、あるあるです。月に数百円のコスト増で、この問題を回避できるなら安いものです。
それから、SecretManagerは最初から使っておくべきです。環境変数に直接シークレットを書くのは楽ですが、後で移行するのが面倒なんです。GitHubに誤ってプッシュしてしまうリスクもあります。最初からSecretManagerを使っておけば、こういった事故を防げます。ボリュームマウント方式を選んでおけば、アプリケーションコードはファイルを読むだけなので、ローカル開発との違いも最小限で済みます。
監視に関しては、エラー率とP95レイテンシのアラートだけは絶対に設定しておくべきです。他のメトリクスは後から追加できますが、この2つがあれば、致命的な問題は必ず検知できます。アラートの閾値は、最初は緩めに設定して、誤検知が多ければ徐々に厳しくしていく方が、運用の負担が少ないです。
最後に、GPUは必要になってから考えればいいです。2026年の新機能として魅力的ですが、普通のWebアプリケーションやAPIには不要です。LLMの推論や画像処理など、明確な用途がある場合にのみ検討しましょう。それまでは、CPUとメモリの最適化に集中した方が、コストパフォーマンスが高いです。
結局のところ、CloudRunは「小さく始めて、必要に応じて成長させる」のに最適なプラットフォームです。最初から完璧な設定を目指すより、まずデプロイして、実際の使用状況を見ながら最適化していく方が、圧倒的に楽だし効率的です。それがサーバーレスの本質だと思います。
CloudRunに関する疑問解決
CloudRunとCloudFunctionsの違いは何ですか?
CloudRunとCloudFunctionsは、どちらもサーバーレスのコンピューティングサービスですが、いくつかの重要な違いがあります。CloudRunはコンテナベースで、どんな言語やフレームワークでも使用できますが、CloudFunctionsは特定の言語ランタイム(Node.js、Python、Go、Javaなど)に限定されています。また、CloudRunは長時間実行されるリクエストに対応できますが、CloudFunctionsには実行時間の制限があります。柔軟性とカスタマイズ性を求める場合はCloudRun、シンプルな関数を素早くデプロイしたい場合はCloudFunctionsが適しています。
コールドスタートの遅延を減らすにはどうすればいいですか?
コールドスタートは、ゼロスケーリング状態からインスタンスを起動する際に発生する遅延です。これを減らすには、最小インスタンス数を設定することが効果的です。最小インスタンス数を1以上に設定することで、常に稼働しているインスタンスを維持でき、コールドスタートを回避できます。ただし、最小インスタンス数を設定すると、アクセスがない時間帯でも料金が発生するため、コストとパフォーマンスのバランスを考慮する必要があります。また、コンテナイメージのサイズを小さくする、依存関係を最小限にする、といった最適化も効果的です。
CloudRunで使用できるメモリとCPUの上限はいくつですか?
2026年2月時点では、CloudRunで使用できるメモリは最大32GiB、CPUは最大8vCPUまで設定できます。ただし、GPU使用時は異なる制約があります。NVIDIA L4 GPUを使用する場合は最低4CPU・16GiBのメモリが必要で、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPUを使用する場合は最低20CPU・80GiBのメモリが必要です。また、リージョンによって利用可能なリソースの上限が異なる場合があるため、公式ドキュメントで確認することをお勧めします。
VPCネットワークに接続できますか?
はい、CloudRunはVPCネットワークに直接接続できます。ServerlessVPCAccessコネクタを使用することで、CloudRunからVPC内のリソース(CloudSQL、Compute Engineインスタンス、内部ロードバランサーなど)に安全にアクセスできます。また、Direct VPC egressという機能も提供されており、より効率的にVPCネットワークに接続できます。これにより、プライベートなマイクロサービス間通信や、データベースへの安全なアクセスが可能になります。
CloudRunでバッチ処理を実行できますか?
はい、CloudRunJobsを使用することで、バッチ処理を実行できます。CloudRunJobsは、HTTPリクエストに応答しない、実行完了型のタスクを実行するためのリソースタイプです。最大24時間実行でき、複数のインスタンスを並列で実行することもできます。定期的なデータ処理、レポート生成、データベースのバックアップなど、スケジュールされたタスクに最適です。また、CloudSchedulerと組み合わせることで、cron式を使用して定期的に実行することも可能です。
まとめ
CloudRunは、サーバーレスアーキテクチャを簡単に実現できる強力なプラットフォームです。本記事では、CloudRunの基礎知識から、2026年2月時点の最新アップデートまで、幅広く解説しました。
自動スケーリング、従量課金制、簡単なデプロイプロセス、言語の柔軟性、充実したセキュリティ機能という5つの特徴により、CloudRunは多くの開発者に選ばれています。特に2026年の最新アップデートでは、NVIDIA L4 GPUとRTX PRO 6000 Blackwell GPUのサポート、WorkerPoolsという新しい実行モデル、SecurityCommandCenterとの連携、IAP統合など、さらに強力な機能が追加されました。
SecretManager、Datadog、CloudLoggingなど、他のGoogleCloudサービスとの連携により、CloudRunの可能性はさらに広がります。実践的な使い方を理解し、適切な設定を行うことで、安全で効率的なアプリケーション運用が可能になります。
サーバーレス開発の第一歩として、CloudRunは最適な選択肢です。無料枠も提供されているため、まずは小さなプロジェクトから始めて、徐々にスキルを磨いていくことをお勧めします。2026年もCloudRunの進化は続くでしょう。最新情報をキャッチアップしながら、CloudRunを使いこなして、効率的なアプリケーション開発を実現してください!
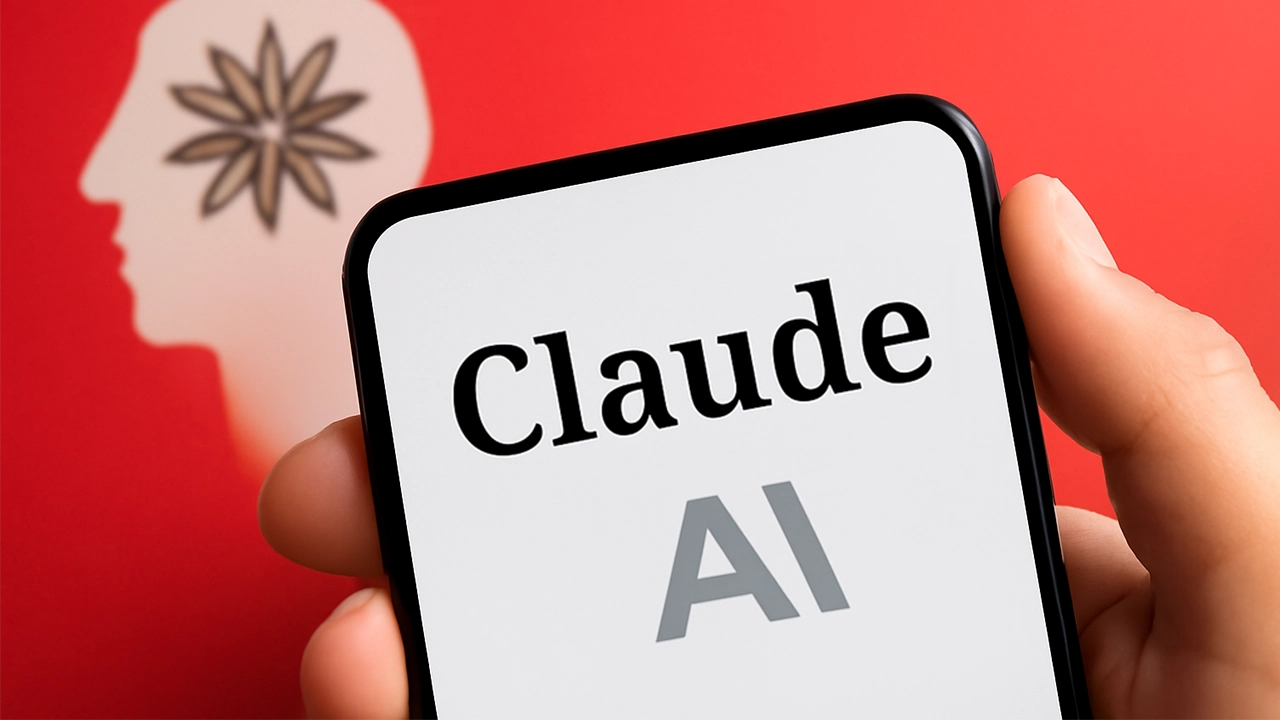


コメント